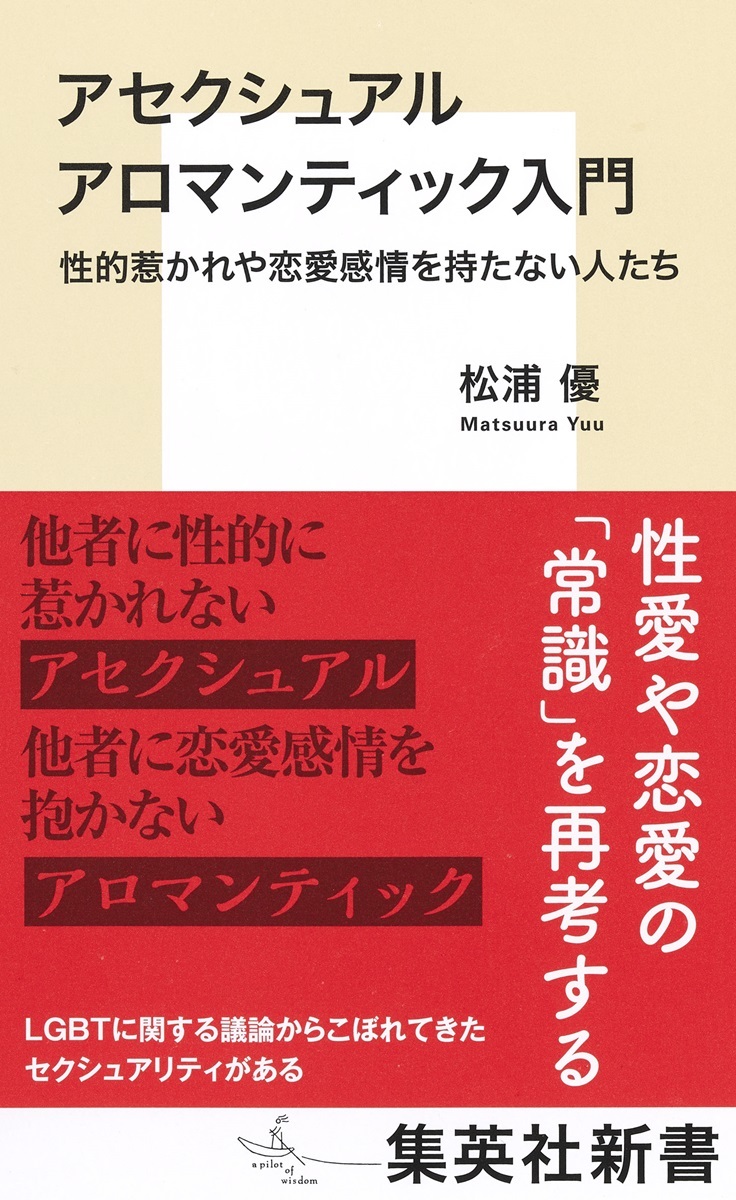2025年2月17日に集英社新書から『アセクシュアル アロマンティック入門:性的惹かれや恋愛感情を持たない人たち』が刊行されます(※「アセクシュアル」と「アロマンティック」の間に半角スペースが入っています)。書店での予約も受付中です。
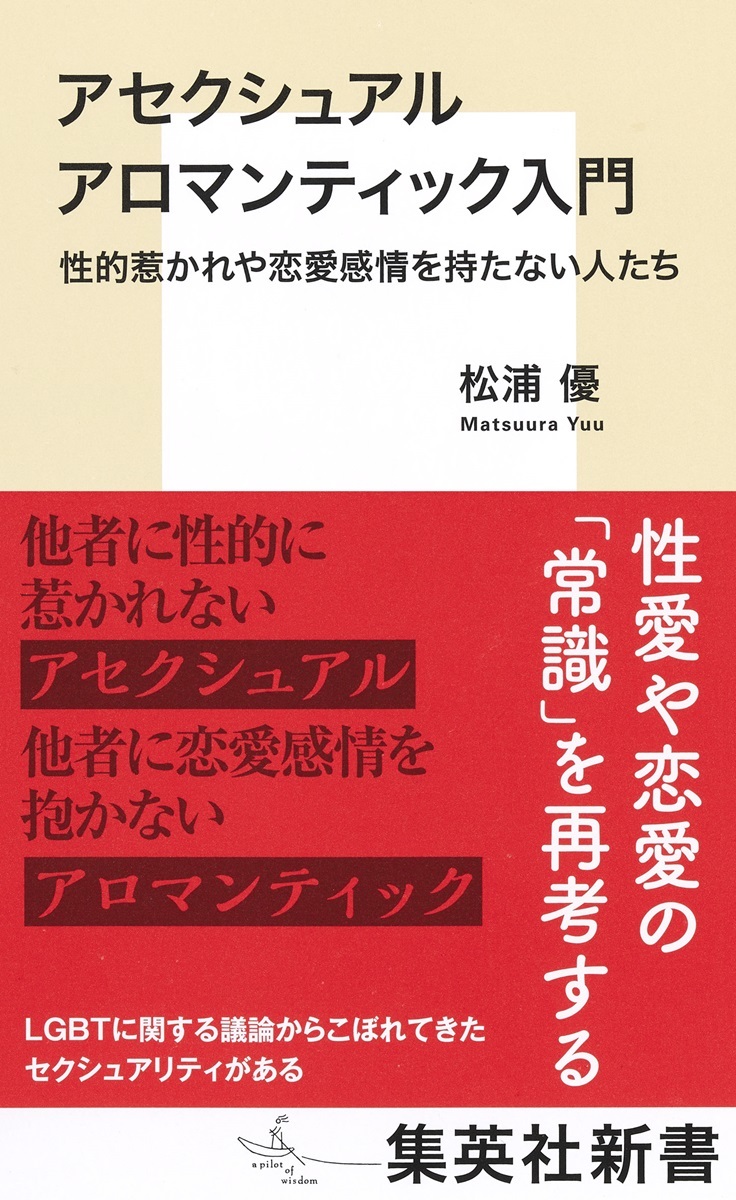
日本語の本としては、すでにアセクシュアル関連の翻訳書が複数あるほか、2024年には日本の当事者コミュニティに根ざした解説書として、『いちばんやさしいアロマンティックやアセクシュアルのこと』(明石書店)が刊行されました。『いちばんやさしい~』はタイトルのとおり、最初に読むのにオススメな素晴らしい本ですので、ぜひ『アセクシュアル アロマンティック入門』とあわせて手に取ってみてください。
さて、本書はそれらに続く新たなAro/Ace本ということで、今までの本とはすこし違うアプローチで書いてみました。本書のコンセプトはずばり、「Aro/Aceからのクィア・スタディーズ入門」です。どんな感じの内容なのか、目次に即してざっと紹介してみます。
目次
はじめに
第1章 アセクシュアル/アロマンティックとは何か
第2章 Aro/Aceの歴史
第3章 Aro/Ace の実態調査
第4章 差別や悩み
第5章 強制的性愛とは何か
第6章 セクシュアリティの装置
第7章 結婚や親密性とセクシュアリティの結びつき
第8章 Aro/Aceの周縁化を捉えるために
第9章 Aro/Aceのレンズを通して見えてくるもの
あとがき
第1章 アセクシュアル/アロマンティックとは何か
この章では、「アセクシュアル」や「アロマンティック」、「性的惹かれ」「恋愛的惹かれ」といった、Aro/Aceに関する議論でよく登場する基本的な用語を解説しています。さまざまなアイデンティティのラベルを紹介しているのに加えて、そのような「新しい用語を作る意義」が何なのか、という点についても説明をしています。
第2章 Aro/Aceの歴史
この章ではAro/Aceの歴史を、性科学や精神医学の歴史、フェミニズムやクィア運動のなかでの議論、そして現在のコミュニティに直接つながる流れ、という観点から解説しています。
現在では、Aro/Aceであること自体は病気ではないと認識されています。しかし歴史的には、性科学や精神医学では、性的な欲望や関心を持たないことは病気だとみなされてきました。まずはそのような歴史について、19世紀以降の議論を(ごく簡単にではありますが)紹介しました。
そのうえで、英語圏において自らを「アセクシュアル」と表明する人々が登場した歴史的事例について紹介しつつ、現在のようなアセクシュアル/アロマンティック・コミュニティが出来る流れを概説しました。
最後に日本におけるAro/Aceの歴史について、1990年代以降の流れを紹介しています。日本での歴史についてはまだまだ研究途上ですので、本書での記述はごくかぎられたものです。それでも、オンラインコミュニティ以前に「アセクシュアル」という言葉が用いられていたことや、日本独自の用語として「ノンセクシュアル」概念が出来上がる経緯について解説しているほか、現在はほとんど使われていない「WSD」という(これまた日本独自の)用語についても触れたりしています。決して網羅的ではありませんが、今後のAro/Ace史をめぐる議論の踏み台になればと思います。
第3章 Aro/Ace の実態調査
この章では、2023年に実施された全国調査「家族と性の多様性にかんする全国アンケート」や、AsLoopが定期的に実施している「アロマンティック/アセクシュアル・スペクトラム調査」などのデータをもとに、Aro/Aceの人々の実態について解説しています。既存の調査をまとめた章ですので、さらに詳しく知りたい方は、各調査の報告書をご覧ください。
第4章 差別や悩み
前章で挙げた調査などをもとに、Aro/Aceの人々が被る差別の状況や、当事者の悩みについて、統計的な分析と具体的な事例を紹介しています。また、日本での調査結果と英語圏での研究をあわせて、Aro/Aceに対する差別をどう捉えるべきかを整理しています。基本的には先行研究を整理したものなので、オリジナルな議論をしているわけではありませんが、重要な論点ですので、ぜひ読んでいただければと思います。
第5章 強制的性愛とは何か
4章まではAro/Ace概説という感じですが、5章以降はAro/Aceの状況やAro/Aceの立場からの問題提起をどう引き受けていくか、より広い文脈から考えていきます。
まず5章では「クィア」とは何か、クィア・スタディーズでよく出てくる「○○ノーマティヴィティ(~規範性)」とは何なのか、という解説をします。その際に「異性愛規範」や「強制的異性愛」について説明したうえで、Aro/Aceの立場から提起された用語である「強制的性愛」を解説します。あわせて、婚姻制度批判から出てきた「恋愛伴侶規範」や、日本のオンライン・コミュニティから生まれた「対人性愛中心主義」などの用語も紹介しています。
こうした規範性をどう理解すべきか。特に強制的性愛について考えるときに示唆に富むのが、ミシェル・フーコーが提起した「セクシュアリティの装置」という概念です。ということで本章では、『性の歴史Ⅰ――知への意志』を中心とする1970年代のフーコーのセクシュアリティ論を紹介し、それが強制的性愛への抵抗にどう役立つかを解説しています。特にフーコーのSM理解がAro/Aceにも示唆的だという話は、今までの日本の解説書には出てこない議論かなと思います。
ちなみにこの章は、「セクシュアリティに関する議論でよくフーコーが出てくるけど、フーコーの文章って小難しいし、フーコー研究には立ち入りたくないから、使えそうなところだけざっくり解説してくれない?」という人向けの文章として書いたつもりです。もっと厳密なフーコー読解がしたい人には、そのための解説書も紹介していますので、うまく活用してください。
セクシュアリティは結婚や親密関係と結びつけられることが多く、特に親密性との結びつきは現代においてむしろ強まっているところがあります。このことをどう考えるか、婚姻とセクシュアリティの関係についてのフーコー的な説明に加えて、婚姻制度と経済システムの関係についてのフェミニズム的な問題提起、さらにアンソニー・ギデンズの親密性論とそれに対する批判などを解説しています(親密性については、最後の9章でもうすこし具体的な話をしています)。
第8章 Aro/Aceの周縁化を捉えるために
この章ではAro/Aceに対する差別や周縁化をより精緻に理解するために、強制的性愛がいかにジェンダーや障害や人種などと交差しているかを解説しています。英語圏での研究蓄積に大きく依拠していますが、同時に日本社会での関連する研究にも目くばせしながら、今後の日本での調査や議論にどう活かすことができるか、日本の文脈に組み込むための議論をしています。
個人的には、「ジェンダーをめぐる差別の問題に関心があるんですね、でしたらAro/Aceについても知っておきましょう」「障害をめぐる差別に関心があるんですね、ではAro/Aceについても(以下略)」「人種をめぐる差別に関心があるんですね、では(以下略)」というノリで書いています。こうした差別を理解するうえでも「強制的性愛」概念が重要だということをお伝えできればと思っています。
第9章 Aro/Aceのレンズを通して見えてくるもの
Aro/Aceから提起された見方は、Aro/Ace以外の人々にも示唆をもたらすものです。そのことを、親密関係をめぐる議論、メディア論、そして「性的」とは何かをめぐる議論を事例に解説しています。
まず、「非モテ」の苦悩や独身差別、そして家族制度や結婚制度の問題などを考えるうえでも、Aro/Aceの立場からの問題提起はとても参考になります。7章で触れた親密性に関する話題を、現代日本の事例に即してもうすこし具体的に書いています。
また批評や表象分析について、ドラマや小説などの登場人物のうち、Aro/Ace自認を明言していないけれどAro/Ace的に読むことのできるような事例をどう捉えていくか、という議論も紹介しています(この議論は歴史上の人物について考えるときにも参考になるものです)。「批評に関心があるんですね、じゃあAro/Aceの議論も押さえておいてください!」ということです。
さらに日本のオタク論やBL研究をAro/Ace的に再評価したり、映画研究者トム・ガニングの「アトラクションの映画」論の(やや思い切った)再解釈をしたりと、私の趣味全開な話もしています。「オタク論とかマンガ研究とかに関心があるんですね、じゃあAro/Aceの議論が参考になりますよ!」という感じです。
そしてAro/Aceからの問題提起は、「『性的』とは何なのか」についても再考を促します。このことについて、BDSMや性的空想に関する議論をもとに問題提起をしています。
このように、Aro/Aceの観点からの議論は、セクシュアリティや恋愛に関する「常識」に問いを投げかけるものでもあります。単に「セックスや恋愛をする気がない人や苦手な人もいるのだから、そうした人々に対して配慮してあげるべきだ」というだけの話ではなく、性愛や恋愛に関する考え方の枠組み自体が問われているのです。
これが本章の(そして本書全体)の核心にあたる主張です。本書全体を通して、セクシュアリティについて、セクシュアリティをめぐる差別や周縁化について、どう考えていくべきか、今後の方針を提示したつもりです。
おわりに
本書の概要は以上です。
Aro/Aceに関する現代的な研究は、特に英語圏では20年ほどの蓄積があります。また日本でも、ここ数年で研究がある程度出てきています。こうした蓄積を一般向けに解説するのが、本書の役割のひとつだと思っています。あくまで現時点での暫定的なまとめではありますが、今後の議論の踏み台として使っていただければ幸いです。ぜひご活用ください。